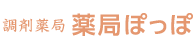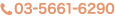こんにちは。薬局ぽっぽの大平です。
前回は食べ物が口に入ったあと、どのように体の外へと出ていくのかをお話ししました。
今回は小腸で栄養が吸収される過程について前編と後編に分けてお話しします。
効率よく栄養を吸収する「ヒト」
高性能ゆえに、今では「貯蓄」が増えやすく…?!
人間の歴史を紐解いていくと、氷河期の時代からマンモスなどの大型動物の狩猟を失敗し獲物が手に入らなかったり、農作物の収穫が天候や疫病などに左右されたりと近代に至るまで安定して食料が得られていたわけではなく、常に飢餓の恐怖に怯えて生活をしていました。
食事事情が改善したのは戦後の話しであり、人類が誕生してからの長い歴史の中でもほんの数十年のことになります。
そのためヒトの体は少ない食事量でも生きぬいていけるように、効率よく栄養が体に吸収・貯蓄されるように設計されています。食べ物が安定して手に入るようになったここ数十年でもヒトの構造や臓器の働きは変化していません。
つまり、昔と異なり食べ物に溢れている現代では食べる量や食べるものに気を付けないとむしろ脂肪として体にため込みすぎてしまう可能性が高くなっているとも言えます。
そのような歴史的背景があるので、効率よく栄養を体に吸収するために消化、吸収に関わるヒトの体の構造は特殊な形をしています。
具体的にはどのような形や働きをもっているのでしょうか。

小腸の長さは約6m!
消化吸収を助けるのは「消化酵素」
栄養の消化、吸収に関わっている部位である小腸は消化管の一部で、十二指腸・空腸・回腸からなり、管がひだ状にうねった形でお腹の中に収まっています。個人差はありますが、その全長は小腸だけでもおおよそ6m以上もあるといわれています。
食べ物がその長い道のりを通ることで無駄なく十分に栄養を体に取り入れることができるのです。
また、食べ物の消化と吸収には消化酵素の働きが必要になります。消化酵素というと一時期テレビなどでも酵素ダイエットなどが流行っていたので耳にしたことのある方もいらっしゃるかもしれません。
酵素と一口にいっても体内で様々な働きがありますが、消化管に存在する酵素は主に食べ物の消化と吸収を効率化してくれる働きがあります。
今回は概要だけになってしまいました。次回は十二指腸にある消化酵素の働きと吸収についてお話しします。